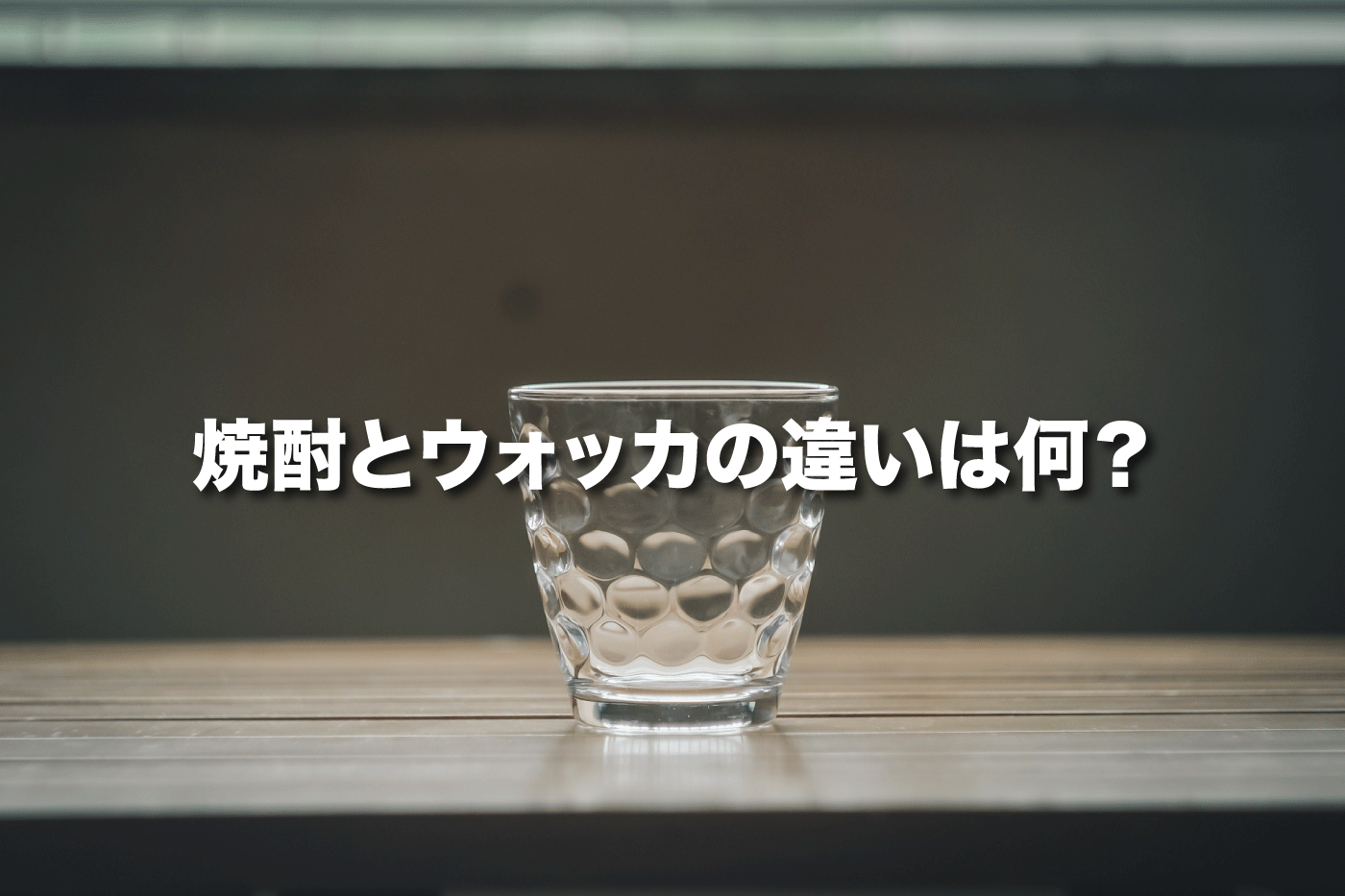焼酎の種類とは? 製造法や原材料の違いを知って焼酎をもっと楽しく!
お酒が好きな人にとって、焼酎がどういった種類のお酒なのか興味のある人は多いでしょう。
焼酎といっても、製造法や原材料といった種類の特徴によって味わいや香りが大きく違います。
それぞれ蒸留の仕方、原材料について、どんな違いがあるのか知っておくと、もっと焼酎が楽しめるように。
それでは、焼酎の蒸留の仕方や原材料による違いについて詳しくみていきましょう。
目次
製造法の違いについて
焼酎は、「蒸留酒」に分類されます。蒸留酒の特徴は、蒸留という工程を経てつくらること。
蒸留に使用される機械は2種類あり、それぞれ「単式蒸留器機」、「連続式蒸留器機」と呼ばれています。
その蒸留機の製造によって3種類の焼酎に分類されます。
ここでは、その「単式蒸留器機」と「連続式蒸留器機」でつくられた焼酎、そしてその2種類をブレンドしてつくられた焼酎をご紹介します。
1.「単式蒸留焼酎」とは
焼酎は、原材料に麹(こうじ)と酵母を加えて発酵させたお酒を蒸留して造ります。蒸留するには専用の蒸留機が必要であると前述しましたが、「単式蒸留焼酎」は、その名の通り「単式蒸留機」という蒸留機で造られます。「単式蒸留機」の主な特徴は1回のみの蒸留であること。その分、原材料の味わいや香りが焼酎に残るので、コクのある焼酎が楽しめます。
酒税法には、「単式蒸留焼酎」の原材料が指定されており、芋や麦、米、黒糖の他に栗、蕎麦、紫蘇などの食物からつくられます。
「単式蒸留焼酎」の焼酎の中には、本格焼酎または焼酎乙類と呼ばれるお酒があります。
さらに、単式蒸留焼酎には、「常圧蒸留法」「減圧蒸留法」といった2種類の蒸留法があります。「常圧蒸留法」は伝統的な蒸留法で、風味が濃厚で複雑。一方、「減圧蒸留法」は歴史が浅い蒸留法で、クセのないすっきりした味わいが特徴。主に大分県の麦焼酎の蒸留法として有名です。
2.「連続式蒸留焼酎」とは
「連続式蒸留焼酎」は、連続式蒸留機という機械によってつくられた焼酎です。連続して何度も蒸溜を繰り返すために、アルコールの度数が90度以上まであがります。その後、水を加えて35度以下に調整されます
「連続式蒸留焼酎」は何回も蒸溜するので、原材料の味わいや香りがお酒に残ることがありません。そのため原材料にこだわりがないのがポイント。実際に、サトウキビから砂糖を精製した後に残る廃糖が原材料に使われています。
「連続式蒸留焼酎」は、甲類焼酎ともよばれています。味わいがピュアでクリアなので、果実シロップや炭酸飲料との相性がバツグン。チューハイやサワーなどのベースのお酒として楽しまれています。
3.混和焼酎
最後の混和焼酎は、上記2種類の蒸留機でつくられた焼酎をブレンドすることによってつくられます。
「単式蒸留焼酎」と「連続式蒸留焼酎」のそれぞれの味わいや香りが楽しめます。
また、混和焼酎は2種類に分類され、甲類焼酎のブレンド率が高いものを「焼酎甲類乙類混和」、乙類焼酎のブレンド率が高いものを「焼酎乙類甲類混和」といいます。
また、甲類焼酎には原材料ごとの区別はありませんが、「焼酎甲類乙類混和 いも焼酎」「焼酎甲類乙類混和 むぎ焼酎」と呼ばれます。
原材料の違い
古くから愛されている芋焼酎
焼酎本来の味わいや香りを楽しみたい方は芋焼酎がおすすめです。焼酎といえば芋焼酎というファンもいるほど人気は絶大。
芋焼酎に使用されている原材料はサツマイモです。サツマイモ特有の甘い香りと豊かな味わいが特徴。代表的な品種は黄金千貫(こがねせんがん)ですが、今では40種類以上のサツマイモが芋焼酎の原材料として使用されています。それぞれの品種には濃厚な甘さ、フルーティな味わいといった個性があります。
古くから鹿児島県や宮崎県といったエリアで生産が盛んです。有名な銘柄はこのエリアでほとんどつくられています。
伝統的な飲み方は、豊かな香りが立ち上がるお湯割りですが、今ではロックやソーダ割りといった飲み方でも楽しまれています。
●おすすめの芋焼酎

霧島酒造は、宮崎県都城市にある蔵元です。「黒霧島」は”クロキリ”として有名な銘柄。麹菌に黒麹を使用して芋焼酎のコクがありながらスッキリした味わいが特徴。
仕込みや割り水に使用される水は、地元の天然水が活躍してふっくらとした飲み心地を支えています。豊かな香りにはお湯割り、スッキリ感を味わいたい場合はロックやソーダ割がおすすめ。
とした
食中酒には麦焼酎
麦焼酎の原料はもちろん麦ですが、中でもお酒造りに適した大麦が使用されます。大麦はビールやウイスキーの原料としても有名です。
麦焼酎の特徴はスッキリした麦の香ばしいキレのある味わい。
ロックやソーダ割りなど様々な飲み方でも楽しめます。また、その爽快感は料理の邪魔をすることがないので、食中酒としても活躍します。
また麦焼酎は、「減圧蒸留」と「常圧蒸留」の蒸留法の違いによって味わいや香りが変わるのがポイントです。「減圧蒸留」は、すっきりしたクリアな味わいに対し、「常圧蒸留」では麦本来の爽快感が楽しめます。
ロックや水割りにすると麦焼酎本来のクリアな香りが味わえます。また、麦焼酎にソーダとレモンを加えて、レモンサワーにするのもおすすめです。
●おすすめの麦焼酎

「兼八」は大分県宇佐市にある四ツ谷酒造が醸造元。「兼八」の特徴は国産の大麦を使用している点。また、一般的に麦焼酎の原料は二条大麦てすが、この銘柄には六条大麦が使われています。そのため麦の香ばしい香りが大きな特徴です。まずはストレートで楽しんで、ロックやソーダ割りにしてマイルドな味わいを楽しむのも良いでしょう。
馴染みのある米焼酎
米焼酎の原料は米。そのため米本来の旨味と甘味が特徴です。米が原料のお酒といえば日本酒が有名ですが、日本酒作りで製造された発酵液を蒸留させたものが米焼酎になります。
その製造方法のため意外に歴史は古く、各地にある日本酒の蔵元でつくられていたといいます。
原料の米は山田錦といった酒米が使用されますが、最近では「コシヒカリ」や「あきたこまち」といったブランド米を使う蔵元もあるようです。
米が持つ豊かなコクと馴染みのある味わいはストレートやロック、ソーダ割りといった様々な飲み方で楽しめます。
●おすすめの米焼酎

「六調子 青」の蔵元は、米焼酎で有名な熊本県球磨にある六調子酒造。この蔵元の歴史は約500年に及びます。
添え仕込みと呼ばれる、一次仕込みは白麹、二次仕込みの際には黄麹を使用する方法を採用。常圧蒸留で仕上げているため、豊かで馴染みのある米の香りと味わあいが楽しめる一本です。ロックにして飲むと、バニラやカシュ―ナッツの香りが味わえます。
味わい深い黒糖焼酎
鹿児島県奄美諸島でしか生産されない「黒糖焼酎」。原料のサトウキビを煮詰めた黒糖からつくられます。黒糖の甘くて芳醇な味わい特徴。30度から20度と同じ銘柄でもさまざまな度数で販売されているので、自分好みの度数を探してみるのもおすすめのポイント。 ロックやソーダ割りにすると、黒糖の甘い香りと味わいが広がります。
●おすすめの黒糖焼酎

鹿児島県奄美の蔵元「山田酒造」の「長雲 一番橋」は、黒糖の芳醇な甘さと香りが特徴の黒糖焼酎です。地元の奄美大島で収穫されたサトウキビを丁寧な仕込みで黒糖を生産。蔵で貯蔵・熟成させ、口当たりは柔らかく、飲みやすい黒糖焼酎に仕上げられています。
製造法や原材料の違いを知ると焼酎が楽しめる
焼酎には製造法や原材料といった違いがあるため、非常に奥深いお酒です。
単式蒸留焼酎・連続式蒸留焼酎・混和焼酎といった3種類の製造法による違い、単式蒸留焼酎では、芋・麦・米を代表とする原材料の違いなどから千差万別の味わいが楽しめるのが、焼酎ならではの特徴。
これからは、製造法や原材料の違いにこだわったり、様々な味わいを楽しんでみてはいかがでしょうか。
この記事を書いた人
SHOCHU PRESS編集部
人気の記事
-
【焼酎の歴史】バクダン・カストリ時代
2021-11-17注目のニュース -
焼酎とウォッカの違いは何?
2022-03-06焼酎の選び方 -
おすすめはウーロンハイ! ウーロンハイの作り方やおすすめの焼酎7選などをご紹介します
2024-09-10焼酎の飲み方