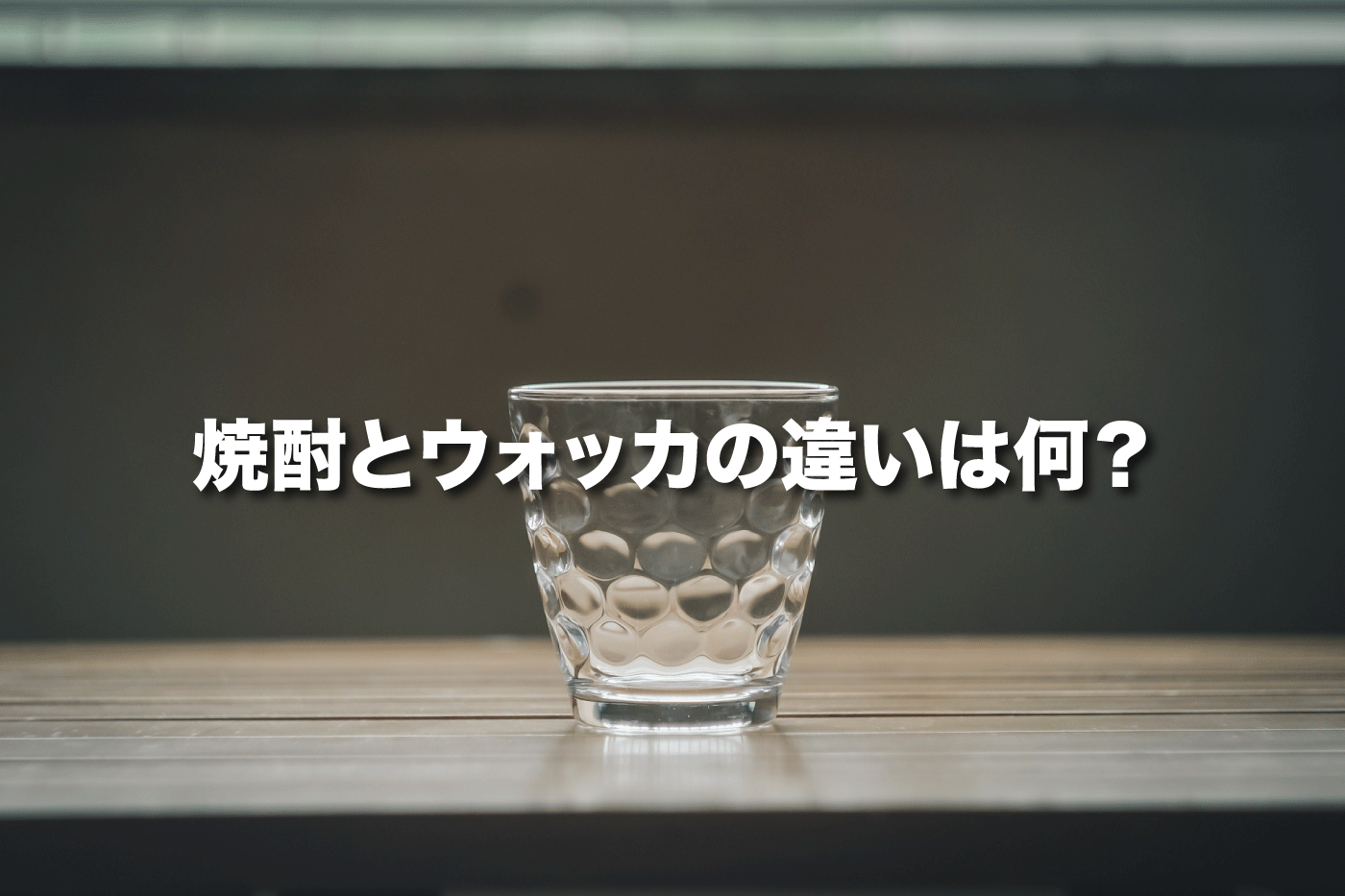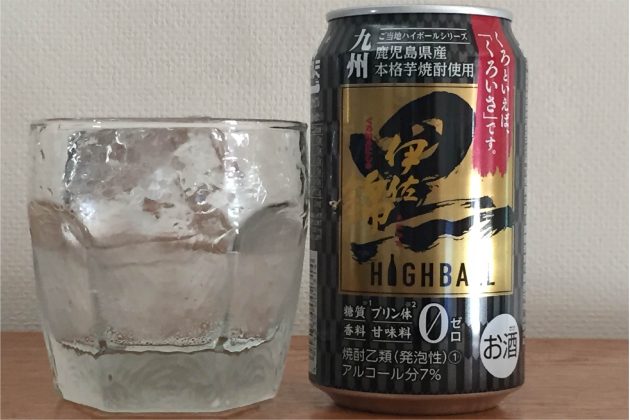ロックは、氷を入れたグラスにお酒を注いだ飲み物。焼酎の飲み方としても人気があります。焼酎はお湯割りや水割り、お燗など飲み方が多彩ですが、ロックはシンプルさが身上。焼酎本来の味わいや香りが楽しめます。今回は、その特徴からおすすめの焼酎までご紹介します。
ロックは焼酎本来の味が楽しめる飲み方
焼酎は飲み方が多彩です。コクのある甘い味わいが特徴の芋焼酎にはお湯割り、クリアでクセのない麦焼酎には水割りなど焼酎の種類によって飲み方が楽しめます。ロックはその中でも、焼酎本来の味を楽しむ飲み方。焼酎と氷のみを使ったシンプルな飲み方だからです。

ウイスキーのように
ロックで飲むお酒といえば、ウイスキーが有名ですよね。
大きめのグラスに入った氷は、ウイスキーの琥珀色を鮮やかに彩ります。
ところで、ウイスキーは食後に飲むお酒といわれています。食事とペアリングするお酒というより、食事が終わった後に飲むお酒。ゆったりとグラスを傾け、ゆっくり味わう、そんなシーンがよく似合います。
一方、焼酎は食事とペアリングする機会が多いお酒。しかし、時には食事が終わった後、ウイスキーのようにゆっくり味わうのも素敵。そんな時はロックがおすすめです。

ロックとストレートの違い
ロックは氷を入れただけのシンプルな飲み方なので、ストレートと似た焼酎本来の味わいが楽しめます。では、ロックとストレートの違いは何なのでしょうか。
それは、氷にあります。
氷の冷たい口あたりは、アルコールのツンとした感じを和らげてくれます。また、焼酎と氷だけなので薄まり過ぎず、反面、ゆっくり味わう間に適度に氷が溶けてアルコール度数が下がるので、飲み口がマイルドに変化します。
焼酎ロックの度数はどれくらい?
ロックは、グラスの氷に焼酎を注いだシンプルな飲み方。氷は時間の経過によって適度に溶け始めます。そのため、アルコール度数が変化するが特徴です。
ゆっくり味わう飲み方なので、焼酎の変化が楽しめます。

ロックは時間とともに、味わいが変化
焼酎のロックは、時間とともに味わいが変化します。
その理由は、氷が焼酎に溶けるため。
焼酎の度数ごとに、経過時間とアルコール度数をご紹介します。
なお、氷の溶けるスピードは、
①室温
②焼酎の温度(冷蔵 or 常温)
③グラスの温度
などによっても変わります。
「焼酎60ml、30mlの氷2個」使用した際の、おおよその度数は下記です。
・20度
半分溶解:アルコール度数13.33度
全て溶解:アルコール度数10度
・25度
半分溶解:アルコール度数16.67度
全て溶解:アルコール度数12.5度
・原酒(40度)
半分溶解:アルコール度数26.67度
全て溶解:アルコール度数20度
氷の溶ける時間は、アルコール度数によって異なる
氷の溶ける時間は、アルコール度数によって異なります。アルコール度数が低い焼酎より、高い焼酎の方が、早く氷が溶けます。これは「凝固点降下」という現象が関係しています。
高いアルコール度数の焼酎をロックで飲む場合に、氷の溶け方が早くなります。

チェイサーを用意
焼酎のロックを飲む際に用意したいのが、「チェイサー」。
「チェイサー」は、一般的には「悪酔い防止のための飲み物」。
バーや居酒屋では、チェイサーといえば「水」が出てくることが多いです。
焼酎ロックは、時間がたつと氷が溶け、アルコール度数は下がります。
それでも酎ハイなどと比べれば、アルコール度数は高め。
だからこそ、焼酎をロックで飲む際は、「チェイサー」を用意するのです。
チェイサーは、お酒の刺激を抑えるだけでなく、脱水症状の防止にも役立ちます。
翌日に残ってしまう方の多くは、お酒による脱水症状が関係しているため、チェイサーをこまめに飲むことで、悪酔いや二日酔いを防止することができます。
美味しいロックの作り方
シンプルな飲み方だからこそ、作り方ひとつで味わいが変わります。
ちょっとしたミスで、焼酎が台無しになってしまうことも。
そこでここからは、美味しい焼酎ロックの作り方を解説していきます。

量の目安は60ml
焼酎ロックを作る際、おすすめの量は「60ml」。これは、「ダブル」といわれる、ロックに適した量です。
「ウイスキー、ダブルで」などと注文をすることがありますが、この「シングル」「ダブル」の意味は、お酒の量を示しています。
「シングル」は30ml。「ダブル」は60mlを指します。
ロックの場合は、60mlの「ダブル」が良いでしょう。
また、お店で作る焼酎ロックは「90ml前後」が基本です。
これは、「ジガー」という計量カップの容量が、45mlだからと考えられます。
ジガー2杯分で、ロック1杯をつくっているのです。
しかし、お酒が強くない方にとって、最初から90mlは多いかもしれません。
そのため、最初は60mlからチャレンジするのがよいでしょう。

氷にこだわる
焼酎をロックで飲む場合、氷が焼酎に溶け出します。そのため、氷の質がとても重要になってくるのです。
水道水で作る氷は、カルキなどの不純物が多く含まれます。
そのため、ロックに使用すると溶けるスピードが早く、風味も濁りがち。
お酒につかう氷は、なるべく市販のロックアイスを使用するのがおすすめです。
良い焼酎、そして良いグラスを用意しても、氷が悪いと台無しに。おいしいロックを楽しむため、是非、氷にもこだわってください。
・ロックアイス
ロックアイスは、大きめのごろごろとした氷です。
コーヒーやジュースなどにも用いられる一般的な氷です。
特徴は、溶けるスピードが早すぎず、薄まりにくいこと。
ゆっくりと時間をかけて楽しみたいなら、ロックアイスがおすすめです。
・クラッシュアイス
クラッシュアイスは、ロックアイスを細かく砕いたものです。
ソフトドリンクやスムージーに使うのが一般的。
特徴は、表面積が大きいため、すぐに冷えること。
さっと注ぎ、さっと飲みたい時に適しています。
また、表面積が大きい分、溶けるのも早くなります。
そのため、少し薄まった状態が良い、という方にもおすすめです。

グラスは大きめのもの
グラスは、大きめのものを用意しましょう。
ロックは氷を入れる分、余裕をもったグラス選びが大切です。
大きめのグラスにたっぷり氷を入れれば、キリッと冷えたロックを作ることができます。
グラスが小さすぎると、お酒の量を調整しにくくなります。
また細すぎると、氷を入れる際にひっかかりやすくなることもしばしば。
かき混ぜる際も、氷でいっぱいだと混ぜにくくなってしまうこともあります。
そのため、グラスは広さに余裕のあるものを選びましょう。

ボトルを冷やす
焼酎ロックを作る際に試していただきたいのが、「ボトルを冷やす」こと。
こうすることで、焼酎を注いだ際、氷が一気に溶けるのを防ぐことができます。
また、常温の焼酎だと、全体が冷えるまでに時間がかかってしまいます。
軽く混ぜて飲んだら、まだぬるくて、おいしくなかった、ということも。
しっかり冷えて、かつ薄くないロックを楽しみたいもの。
そのために、事前に焼酎を冷やしておくのをおすすめします。
ロックに合うおすすめ焼酎
「ロックの楽しみ方はわかったけど、肝心の焼酎は何を買えばいいの?」
という方のために、ロックに合う焼酎をご紹介します。
しそ焼酎 鍛高譚
鍛高譚は、「たんたかたん」と呼びます。
リズム感が、なんとも気持ち良い名前です。
北海道の白糠町(しらぬかちょう)で栽培された赤しそを使用。
そして、北海道中央部の大雪山(たいせつざん)を望む、旭川の水を使用しています。
しそ由来の、華やかで爽やかな風味が特徴です。
鍛高譚は「タンタカ物語」という意味。
詳しく知りたい方は、是非公式ホームページをご覧ください。
(参考:鍛高譚 公式サイト)
いいちこ20度
「いいちこ」と言えば、コンビニなどでもよく見るお馴染みの焼酎。いいちこには「20度」と「25度」がありますが、ロックで飲む場合は、「20度」がおすすめです。
25度は華やかな香りやクセのなさが特徴。
一方の20度は、うまみ成分や味わい深さが特徴。
そうしたうまみ、深い味わいを楽しむために、ロックおすすめなんです。
味の濃くない、魚料理などと合わせると深い味わいが楽しめるでしょう。

黒霧島
伝統的な「黒麹」を使用している「黒霧島」も、ロックにおすすめの焼酎です。
黒霧島の特徴は、トロっとした甘みと、キリッとした後味。
食中酒として大人気で、どんな料理とも相性が良い焼酎です。
芋臭さなど嫌なクセもなく、芋焼酎が苦手な方でも飲みやすい「黒霧島」。
こちらも、ロックなどで楽しみたい一本です。

球磨焼酎
「球磨焼酎(くましょうちゅう)」は、
熊本県球磨郡や人吉市でつくられる米焼酎の総称です。
200以上の種類があり、コクのあるものからさっぱりとしたものまで、様々な球磨焼酎があります。
しかし全てに共通しているのは、米焼酎ならではの「食事との相性のよさ」。
お米の甘さがありつつ、スッキリとした味わいの球磨焼酎も、ロックで飲むのに適しています。

樫樽熟成焼酎
「樫樽熟成焼酎」とは、樫をつかった樽で熟成した焼酎のこと。樫樽熟成された焼酎は、風味がまろやかになり、木樽特有の甘みやスモーキーさが楽しめるのが特徴です。
「百年の孤独」は、樫樽熟成焼酎を代表するプレミアム焼酎。
麦焼酎ならではの麦の香ばしさや、優しい木の香りが特徴の銘柄となっています。
こうした樫樽熟成焼酎も、本来の風味を楽しめるロックで楽しむのがおすすめの飲み方。

まとめ
いかがでしたか?
今回は、焼酎のロックの特徴や、おすすめの銘柄などをご紹介しました。
焼酎のロックは、焼酎本来の味わいと香りを楽しめる飲み方。
さらに氷が溶けることによって風味が変わる、とても魅力的な飲み方です。
「いつもはお湯割り」という皆さんも、是非ロックにチャレンジしてみてください。