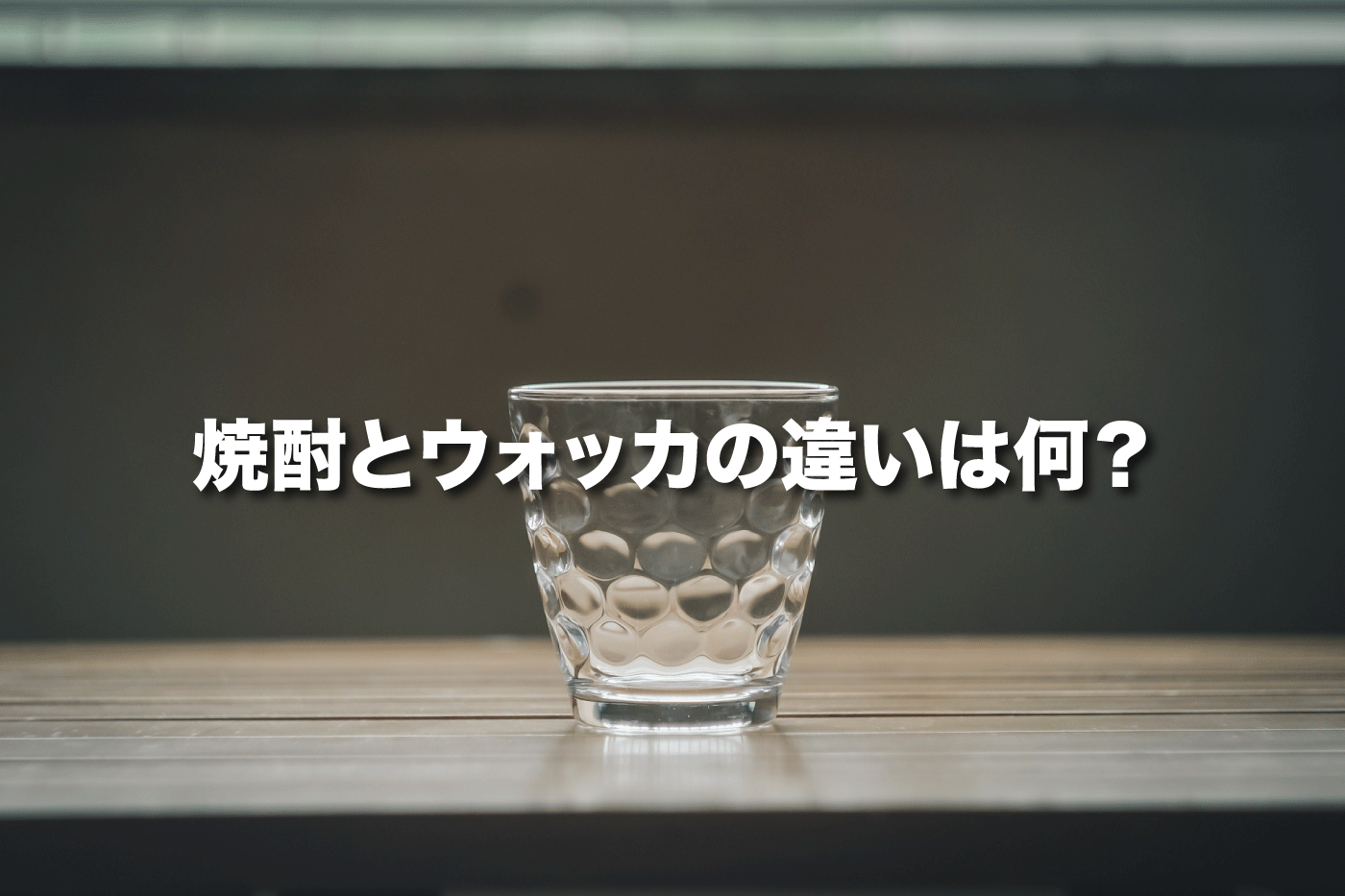【焼酎の歴史】酎ハイは居酒屋が生んだ?居酒屋チェーンと甲類焼酎がつくった国民的ドリンク
チューハイは、いまや居酒屋でも家飲みでも定番の存在。
レモン、グレープフルーツ、梅、無糖タイプまで幅広く、気軽に楽しめるお酒として多くの人に親しまれています。
この「酎ハイ」、実は居酒屋チェーンの現場から生まれたお酒だという説があるのをご存じでしょうか。
戦後の東京下町で飲まれていた焼酎ハイボールをルーツとしながら、
それを“商品”として確立させ、全国に広めたのが居酒屋チェーンだった――。
今回は、酎ハイ誕生の背景と、それを生み出した居酒屋チェーンの物語を、焼酎メディアの視点でひも解いていきます。
目次
居酒屋チェーンはいつ生まれたのか?
いまでは駅前やロードサイドに当たり前のように並ぶ居酒屋チェーン。
しかし、日本でチェーン展開が本格化したのは、実はそれほど昔ではありません。
転機となったのは1969年の「第二次資本自由化」。
これにより外資系企業の日本進出が進み、1971年にはマクドナルド、ケンタッキーフライドチキンが相次いで上陸します。
この流れの中で、「統一された店舗・メニュー・オペレーション」を持つチェーンビジネスモデルが一気に注目されました。
高度経済成長の真っただ中。
事業拡大を目指す経営者たちにとって、チェーン展開は理想の形だったのです。
そして1970年代、「養老乃瀧」「村さ来」「つぼ八」といった居酒屋チェーンが次々と誕生していきます。
居酒屋チェーンが最初に直面した「お酒」の問題
「ところが、居酒屋のチェーン化には大きな壁がありました。
それが「酒をどう扱うか」という問題です。
当時の居酒屋で主流だったのは、ビール、日本酒、焼酎といったメーカー商品。
注ぐだけで提供できる反面、
・価格はメーカー主導
・原価率が高い
・店独自の利益商品になりにくい
という弱点がありました。
チェーン展開を進めるには、「安定して仕入れられて、原価が低く、店の看板になる酒」が必要だったのです。
そこで注目されたのが、甲類焼酎でした。
酎ハイを生み出した居酒屋チェーン「村さ来」
この流れの中で酎ハイを“商品”として形にした人物が、居酒屋チェーン「村さ来」の創業者・清宮勝一氏です。
当時の甲類焼酎は、東京の赤ちょうちんで
・焼酎+炭酸
・焼酎+甘味シロップ
といった形で飲まれていました。
いわば、庶民のための割りもの焼酎です。
清宮氏はこの飲み方に目をつけ、あえてそれをチェーン居酒屋の主力商品に据えました。
ただし、狙ったのは従来の酒飲み層ではありません。
ターゲットは「若者」でした。
若者向けに再設計された「酎ハイ」という飲み物
清宮氏が行った最大の工夫は、飲み方のデザインです。
・ビールジョッキで提供
・アルコール度数は低め
・がぶ飲みできる設計
・味は甘く、飲みやすく
さらに、フレーバー展開にも力を入れます。
レモン、グレープフルーツだけでなく、ライム、オレンジ、みかん、ゆず。
さらにはウーロン茶割り、日本茶割り、カルピス割りまで。
最盛期には120種類以上あったともいわれています。
「若者がファッショナブルに飲める酒」
こうして誕生したのが、いま私たちが当たり前に飲んでいる酎ハイの原型でした。
酎ハイは居酒屋チェーンを成長させた“エンジン”だった
酎ハイは、味だけでなくビジネス的にも革命的でした。
甲類焼酎+炭酸+シロップ。
原価は数十円レベル。
それまで利益が出にくかった「酒」が、一気に高収益商品へと変わったのです。
この酎ハイの成功によって、居酒屋チェーンは
・価格を抑えられる
・客層を広げられる
・回転率を上げられる
という強力な武器を手に入れました。
結果、1980年代には空前の居酒屋ブームが到来。
その中心にあったのが、酎ハイだったのです。
まとめ|何気なく飲んでいる酎ハイの裏側には、焼酎の進化がある
酎ハイの起源には諸説あります。
しかし、「居酒屋チェーンが全国に広めた」という視点で見ると、そこには甲類焼酎の可能性と、居酒屋文化の転換点がはっきりと見えてきます。
いま私たちが気軽に飲んでいる一杯は、実は、焼酎と居酒屋が一緒に進化してきた歴史の結晶。
次に居酒屋で酎ハイを頼むときは、その背景にある物語を思い出しながら、ゆっくり味わってみてください。
きっと、少しだけおいしく感じるはずです。
この記事を書いた人
SHOCHU PRESS編集部
人気の記事
-
【焼酎の歴史】バクダン・カストリ時代
2021-11-17注目のニュース -
焼酎とウォッカの違いは何?
2022-03-06焼酎の選び方 -
おすすめはウーロンハイ! ウーロンハイの作り方やおすすめの焼酎7選などをご紹介します
2024-09-10焼酎の飲み方