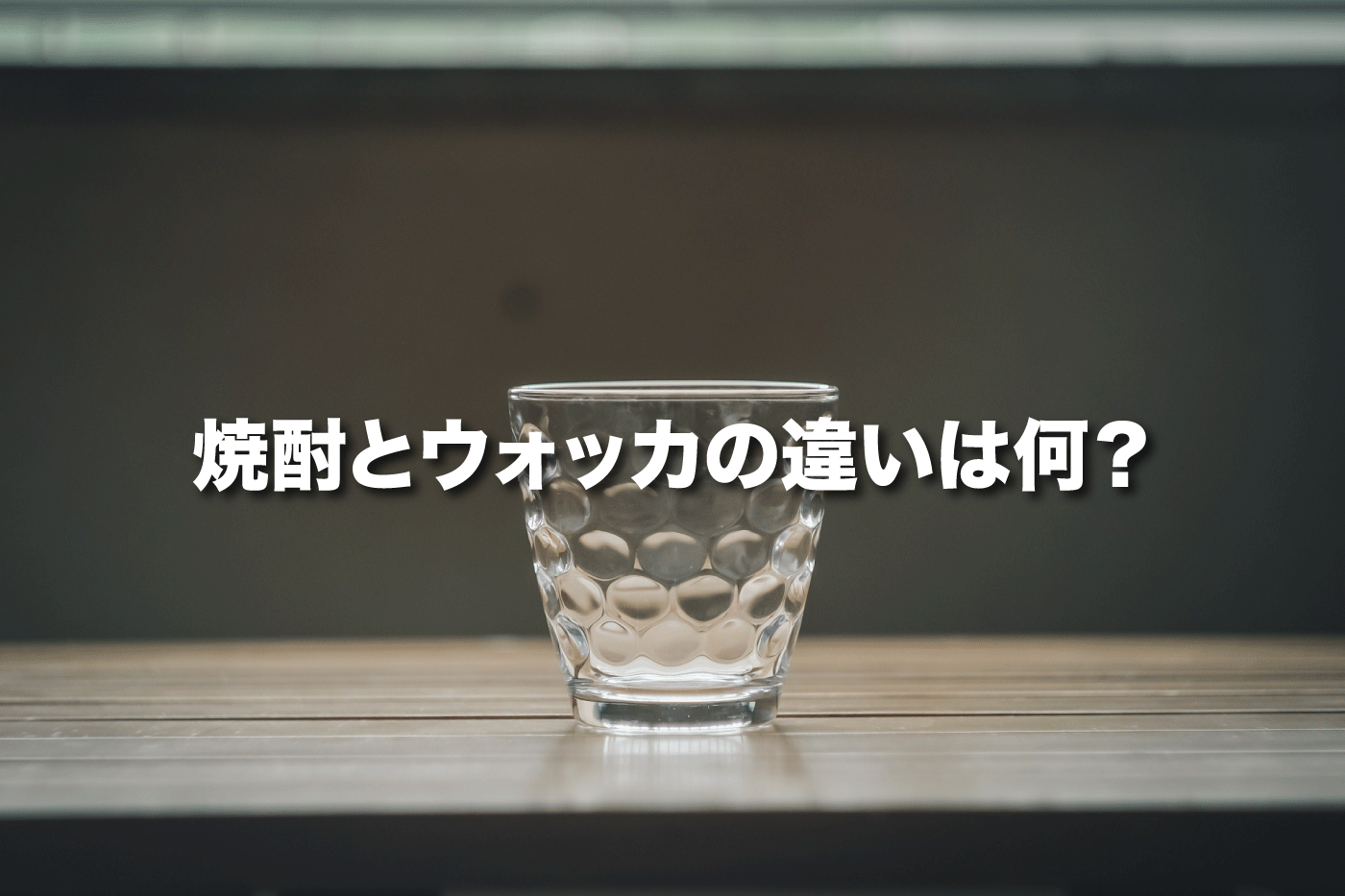香り系焼酎とは? 飲み方やおすすめ銘柄7選をご紹介します!
香り系焼酎が2010年代後半から注目を集めています。
”フレーバー系”焼酎とも呼ばれ、ラベルも凝ったデザインが特徴的。
オレンジやライチ、バナナといった果実以外にも、ワインや紅茶、ヨーグルトなど「どうして芋焼酎からこんな香りが!」と驚くようなフレーバーが続々と誕生しています。
今回は、そんな香り系焼酎をご紹介します!
目次
香り系焼酎とは?
香り系焼酎の銘柄のほとんどは、芋焼酎が主流であるのをご存知でした?
焼酎の原材料には、芋以外にも麦や米、黒糖など豊富にあるのに不思議ですよね。
その理由は、芋焼酎の原材料として使用されるサツマイモにあります。
サツマイモには、花や柑橘と同じ”テルペンアルコール”という成分があります。
その”テルペンアルコール”が製造過程で花開き、香り系焼酎の元となるのです。
芋焼酎に含まれる”テルペンアルコール”は、1Lあたり1000分の数十㎜gしか含まれていませんが、香りに大きな影響を与えています。
例えば、香り系焼酎の代表フレーバーであるライチの風味は、”テルペンアルコール”の中のシトロネロールが由来。
かつての伝統的な芋焼酎は、「クセが強い」と表現されていました。
サツマイモが原料の芋焼酎には、独特の蒸れたような香りがあり、一部の人に敬遠されるほどだったといいます。
今では、その”香り”が強みとなり、芋焼酎の新しいジャンルにつながったことはとても興味深いことですよね。

香り系焼酎の誕生
香り系焼酎は、国分酒造の安田宣久氏の仕事によって誕生しました。
安田氏が1998年(平成10年)に開発した、「安田」という銘柄が香り系焼酎の元祖といわれています。
安田氏は香り成分”テルペンアルコール”以外にも、サツマイモの収穫時期を遅らせたり、熟成させるなど製造方法を研究。
その研究が結実した成果が、香り系焼酎なのです。
安田氏の研究は継続し、2018年(平成30年)に今では大変な人気銘柄となった「flamingo orange」を誕生させます。
鹿児島県工業技術センターが開発した香り酵母(鹿児島香り酵母1号)を使用したことにより、香り系焼酎を安定的に生産することに成功。
オレンジやライチなど果実香があふれる「flamingo orange」は、香り系焼酎というジャンル確立の先駆けとなったのでした。
おすすめの香り系焼酎7選
現在では、香り系焼酎は焼酎のトレンドとなり、各焼酎メーカーがこぞって開発し販売しています。
その中でもおすすめ香り系焼酎の銘柄を7選ご紹介したいと思います。

「flamingo orange」(フラミンゴオレンジ)」国分酒造
2018年(平成30年)6月に販売された「flamingo orange」は、香り系焼酎の代表銘柄です。
ブルゴーニュワインのようなその容姿は、各メディアでも取り上げられているので、ご存知の方も多いはず。
容姿の似た兄弟銘柄である「coolmint green(クールミントグリーン)」「sunny cream(サニークリーム)」もそれぞれ人気。
グラスに注ぐと広がるオレンジやライチの香りは、香り系焼酎の最高峰です。

GLOW EP05 若潮酒造
「GLOW EP05」は、「酒屋が選ぶ焼酎大賞」で3年連続の大賞を受賞。殿堂入りを果たしました。
ライチとグレープフルーツの香りを両立させた、すっきりした飲み心地の香り系焼酎。
サツマイモの病気である基腐病が流行したため、予定していたものと違う品種で仕込みを使用することになった「GLOW EP05」。
その結果、この”フレーバー系”焼酎が生まれたといいます。

「彩響(アヤヒビキ)」薩摩酒造
焼酎の香り研究は、各メーカー凌ぎを削っていますが、「彩響(アヤヒビキ)」の特徴といえば、清酒酵母を使用した低温発酵。
そのため、他の香り系焼酎のフレーバーとは別次元の青リンゴのような爽やかな香りを実現させました。
冷涼感のあるボトルも気分を盛り上げます。
また、蔵元の薩摩酒造は、「彩響(アヤヒビキ)」の飲み方としてソーダ割りを推奨しています。

「乙女桜」さつま無双
「乙女桜」に使用されているサツマイモは、紅乙女芋。
名前の由来は、皮身が綺麗な紅色で、すらりとした乙女のようだから。
仕込みはサツマイモの収穫後、一定期間熟成させるといいます。
そのため、フルーティなライチのような香りが立ち上ります。
優しい甘み、軽快な飲み口は心地よい味わいが身上の香り系焼酎。
蔵元のさつま無双は、ソーダで割る「乙女ハイボール」や、トニックウォーターで割る「乙女トニック」などの飲み方をオススメしてます。

「だいやめ -DAIYAME-」濱田酒造
「だいやめ -DAIYAME-」は今ではスーパーなどでも取り扱っており、一番見かけることの多い銘柄となりました。
「香熟芋」を使用した独自の熟成法で香り引き出すことに成功。
ライチの甘い香りは果実味あふれ、多くのファンに支持されています。
世界三大酒類コンペティションに出品して、2019年「IWSC」でSHOCHU部門最高賞を受賞。
世界的な評価を獲得した、香り系焼酎です。
「霧島8(キリシマエイト)」霧島酒造
「黒霧島」で有名な霧島酒造が販売する香り系焼酎。
2023年2月に全国に先駆けて首都圏で販売し、翌年の2024年7月に900ml瓶で全国で展開。
半年ほどで25万本を売り上げ、2年間で累計42万本を突破して、香り系焼酎として異例の大成功を納めたました。
果実香を豊富に生み出すさつまいもを自社開発。
37通りの試みのうち、8番目の交配となる「タマアカネ」と「シモン1号」の掛け合わせから新品種が誕生。
「霧島8(キリシマエイト)」という銘柄名はこのストーリーが由来といいます。

「克 無手勝流(かつ むてかつりゅう)」東酒造
克 無手勝流(かつ むてかつりゅう)」の最大の特徴は、瓶を開けた瞬間に広がるマスカットのような爽やかな香り。
また口に含むとライチを感じさせる甘い味わいが感じられます。
銘柄名の”無手勝流”とは戦わずして勝つという意味。「比較されない唯一無二の焼酎を目指す」という蔵元の願いが込められています。
日本古来の伝統色「勝色」でラベルカラーに採用したのも、勝負にこだわる克を体現するためだといいます。
香り系焼酎のオススメの飲み方
香り系焼酎の見た目は、今までの焼酎とは一線を画すデザインが特徴。
飲み方も、従来のお湯割りやストレートとった違ったソーダ割などを各メーカーは提案しています。
それでは、香り系焼酎のおすすめの飲み方を紹介します。

ソーダ割り
焼酎の飲み方は、伝統的なお湯割りやストレート、水割りが一般的ですが、香り系焼酎はソーダ割りが似合っています。
お酒をソーダで割る飲み方といえば、ハイボールが有名ですよね。
ソーダのシュワシュワが、ツンとしたアルコールの感じを和らげてくれると共に、立ち上るような香りを楽しむ飲み方といえます。
香り系焼酎のような、香りがギュッと詰まったお酒にはお似合いの飲み方といえます。

トニック割り
トニック(トニックウォーター)は、ほのかな苦みと甘みのあるドリンクです。
糖分にキナ、ハーブ、柑橘類のエキスを加えた炭酸水でお酒との相性が良くカクテルに使われることが多いです。
ジントニックに使用されることで有名ですよね。
香り系焼酎の持つ風味とトニックの爽快感は、相性の良い飲み方です。

ロック
香り系焼酎をすっきりと飲みやすく、かつ独特の風味も楽しみたいなら、ロックがオススメ。
氷で冷やすと甘味が締まるとともに、とろりとした質感になり、香り系焼酎を味わうには相応しい飲み方です。
ストレートに近い飲み始めから、時間の経過とともに氷が解けて水割り状になるので、果実系の香りの変化も楽します。
まとめ
いかがでしたか?
従来の焼酎のイメージを大きく変える焼酎として、香り系焼酎が注目を集めているのをおわかりいただけましたか。
今後はさらに、多くのファンに浸透していくことでしょう。
酒屋やスーパーで、香り系焼酎を見かけたら、立ち止まって注目してみてくださいね。
この記事を書いた人
SHOCHU PRESS編集部
人気の記事
-
【焼酎の歴史】バクダン・カストリ時代
2021-11-17注目のニュース -
焼酎とウォッカの違いは何?
2022-03-06焼酎の選び方 -
おすすめはウーロンハイ! ウーロンハイの作り方やおすすめの焼酎7選などをご紹介します
2024-09-10焼酎の飲み方